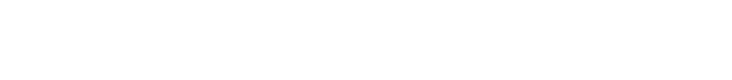高齢の方や障害をお持ちの方が家族にいる場合、階段の昇り降りはとても気を使います。万が一転倒したら…という心配をしないためにも階段をバリアフリー化しませんか?今回は階段のバリアフリー工事の費用相場や介護保険、補助金を利用する方法などを解説していきます。
階段をバリアフリー化するには?6つのリフォーム箇所を徹底解説!

階段は高齢者や障がい者にとって大きな事故につながりやすい場所のため、バリアフリー工事がおすすめ。なるべく安全に自由に家の中を行き来できるよう、早めに対策が必要です。こちらでは6カ所の階段バリアフリー工事をご紹介していきますので、複数の工事をを組み合わせるなどして使いやすい階段にしましょう。
階段の勾配を緩くして段差を変える
通常は45度程度ある階段の勾配を緩くしたり一段の段差(蹴上げ)を小さくすると、高齢者でも階段がずいぶん上りやすくなります。さらには足を踏み込む「踏み面」の奥行を広くするのも有効。階段のバリアフリー化に有効な寸法は以下の通りです。
- 勾配・・・25~35度
- 蹴上げ・・・15~18㎝
- 踏み面・・・25~32㎝
このように階段の段差を低くして踏み面を広げると、高齢者でも転倒しずらく昇りやすい階段になります。このバリアフリー工事は階段の安全性を高める上でとても効果的なので、二階への昇り降りを頻繁にする高齢者のいる家庭では、ぜひ取り入れてください。
階段の両側に手すりを設置
同時に階段の両脇に手すりを設置すると、階段での転倒が予防できます。2000年に改訂された建築基準法では、住宅の階段に手すりを設置することが義務化されました。とはいえ一般家庭では片側だけに付けることが多いため、バリアフリー工事では両側に手すりを付けることをおすすめします。
通常階段に手すりを取り付ける際には、降りる時の利き手側に設けます。ただし足腰が弱い方や高齢者にとっては、階段を昇るのもつらい動作となります。そこで手すりで体を支えることで、体への負担を軽減させられるという訳です。
階段の手すりには形や設置方法から次のような種類があります。
- 一直線型・・・従来の手すりによく見るタイプ
- L字型・・・縦と横に伸びた手すり
- 据え置き型・・・壁に穴を開けなくても使える
- はね上げ型・・・必要ない時は収納できる
据え置き式の手すりは階段の踏み面に固定するので、片側に壁が無くても大丈夫。手すりの高さは踏み面の先端から70~90㎝の高さが一般的ですが、使う方の身長や手の位置に合わせて設置しましょう。
さらに手すりの表面に滑り止め加工を施してあるタイプや、力が弱くても握りやすい形状の手すりにすることで安全性がよりアップします。
階段昇降機を設置する
移動に車いすを使用している方や自力で階段を昇り降りできない要介護者のいる家庭では、階段に昇降機を設置するという方法があります。昇降機とは階段脇に取り付けたレールを伝って、座っているだけで昇り降りできる機械式のリフトのこと。バリアフリーリフォームで後付けができ、駅などでも採用されています。
家の1階だけで生活できない、2階に要介護者がいるなどの場合にも安全に移動ができます。ホームエレベーターという方法もありますが、大規模な改修工事となり費用も掛かるため、階段昇降機を設置するお宅が増えています。
足元を照らす照明を追加
階段のバリアフリー化では、足元部分に照明をつけるという工事があります。天井に階段を照らす照明が付いている住宅は多いですが、足元に照明をつけている住宅はまだ少ないのではないでしょうか?夜中にトイレなどで階段を上り下りする際に便利な足元照明は、このような点に注意して取り付けましょう。
- 照度を確保するため50ルクス以上
- 階段の段差で影にならないように取付位置に気を付ける
- 蹴上げと踏み面の色を変えるなどの工夫が必要
特に照明の取り付け位置に注意が必要です。あまり低すぎると照らしたい場所に影を作ってしまい、かえって見づらくなることも。また人感センサーが搭載された照明なら、暗い場所でスイッチを探さなくてもいいので安心です。
滑りにくく転んでも安全な床材へ変える
階段の踏み面自体を滑りにくい素材にするか、後付けで滑り止めを重ね張りする方法も有効です。ただし自分でゴム製の滑り止めを購入して、それを貼りつけるということはあまりおすすめできません。
貼りつけた滑り止めの高さが高すぎるとそこにつまずいて転倒する恐れがあります。また滑り止めの効果がありすぎると逆に危険性が増してしまいます。
階段の床材を滑りにくくリフォームする場合は、必ず介護リフォームの実績が豊富な専門の業者にお任せしましょう。
踊り場のある階段へ改修する
階段の形を踊り場のあるものへ変更するという工事もバリアフリー化には有効。階段が一直線にある階段はリズムよく昇り降りができますが、一度転倒すると一番下まで転げ落ちてしまう危険があります。そこで階段の途中に踊り場があるU字階段へ変更することで、途中で止まることができます。
また階段の踊り場は、一度上体を起こして一休みする場所にもなります。比較的大規模なリフォームになりますが、勾配を緩くしたり手すりを取り付ける工事も同時に行えますので階段のバリアフリー化には特におすすめです。
階段のバリアフリーにかかる費用相場や日数とは?

では実際に階段をバリアフリー化するにはどの位の費用や日数がかかるのでしょうか。上で説明したリフォーム箇所ごとに解説していきます。
階段の配置換えや段差の変更
直線階段をU字階段に変更したり、段差を緩くする工事は既存の階段のサイズや家の構造によって異なります。おおよその費用相場や日数はこちらです。
| 工事内容 | 費用相場 | 工事日数 |
| 既存階段を解体して直線階段を設置 | 500,000円~ | 3日~ |
| 既存階段を解体してU字階段を設置 | 900,000円~ | 1週間前後 |
| 既存階段を再利用して設置位置を変更 | 450,000円~ | 3~5日 |
上記の工事なら途中に踊り場を設置したり、両側に手すりを取り付ける工事も可能。全体で100万~150万円の予算を見ておけば、階段のバリアフリー工事はトータルで出来るでしょう。
手すりを設置する
階段の両側に手すりを設置する工事は、取り付ける手すりの種類や階段の形によって異なります。
| 工事内容 | 費用相場 | 工事日数 |
| 直線階段に手すりを設置 | 40,000円~ | 1日~ |
| U字階段に手すりを設置 | 75,000円~ | 1日~ |
| LED照明内蔵の手すりを設置 | 100,000円~ | 1日~ |
直線階段とU字階段で設置費用が異なるのは、角部分の処理が難しいためです。手すりを途切らせないようにするには、90度に手すりを曲げるなのど加工が必要になります。また手すりにLED照明が埋め込まれたタイプなどもあるので、使い勝手や費用を比べながら選んでみましょう。
階段昇降機を設置
階段昇降機を階段に設置する場合、レールの種類によって費用が異なります。直線階段には比較的安い直線レールが使えますが、U字階段では曲線レールが必要に。自宅の階段の形によって費用が変わってしまうことを覚えておきましょう。
| 工事内容 | 費用相場 | 工事日数 |
| 直線レールのコンパクトタイプ | 580,000円~ | 1日~ |
| 曲線レールの階段昇降機 | 1,200,000円~ | 1日~ |
足元照明を追加
足元照明はホームセンターなどで自分で取り付けることも可能ですが、業者に頼む場合の費用はこちらです。
| 工事内容 | 費用相場 | 工事日数 |
| 足元照明取付工事(1か所) | 10,000円~ | 半日~ |
ただし足元照明の取り付け工事は、介護保険の適用から外れてしまいます。工事費用は全額実費負担となりますのでご注意ください。
床材の変更費用
床材の変更費用は、その施工法法によって変わってきます。既存の床材の上から滑り止めを重ね張りする方が、床材自体を張り替える工事よりも安くすみます。
| 工事内容 | 費用相場 | 工事日数 |
| 床材を重ね張り | 25,000円~50,000円 | 半日~1日 |
| 床材を張り替え | 40,000円~60,000円 | 半日~1日 |
階段のバリアフリー工事には介護保険や補助金を利用

住宅のバリアフリー工事には介護保険や自治体の補助金制度により、安くできることがあります。また税金の控除を受けられる場合もありますので、工事前に勉強しておきましょう。
介護保険を利用した住宅改修
介護保険制度を利用した住宅のリフォームでは、最大20万円までの補助を1割の自己負担で受けられます。ただし介護保険を利用するにはいくつかの条件があります。
【受給対象者の条件】
- 要介護認定で「要支援」か「要介護」と認定されている
- 改修対象住宅の住居は本人が居住している場所で被保険者証の住所と同一
また介護保険の給付を受けるには、支給対象となる工事に当てはまるか?ということが重要になります。リフォーム工事が条件に当てはまっているか不明な方は、各自治体の介護保険窓口までお問い合わせください。そして給付を受ける手順はこのようになっています。
【給付の手順】
- 介護認定を受ける
- 担当のケアマネジャーへ相談する
- 施工業者・ケアマネジャー立ち合いの元で工事内容を打ち合わせ・契約
- 事前申請に必要な書類を提出し、審査結果を確認
- 工事着工
- 工事終了後に工事費を業者へ支払う
- 領収書や工事費の内訳書、改修完了確認証を提出し介護保険へ申請
- 住宅改修費の支給を受ける
地方自治体の補助金を利用する
お住いの自治体によっては、補助金や助成金が受け取れる制度があります。自治体によって対象となる年齢や工事内容、補助金の上限額が異なります。また上記の介護保険の利用と併用できる場合もありますので、詳しくは自治体の窓口や地元の介護リフォームを行っている業者へお問い合わせください。
減税制度で控除を受けられる
「バリアフリー特定改修工事特別控除制度」とは、下記の条件を満たしている本人か、その同居人が所有し居住している住宅のバリアフリー工事を行った際に、所得税が控除される制度です。
- 50歳以上
- 要介護または要支援の認定を受けている
- 所得税法上の障がい者である
控除対象の限度額を200万円として、その10%を控除できます。控除期間は1年で、工事後に済み始めた場合はその年分のみが適用されます。階段のリフォームではこのような工事が対象となります。
- 階段の勾配の緩和
- 手すりの取り付け
- 滑りにくい床材料への取替え
手続き方法は必要書類を添付して、お住いの税務署で確定申告をしてください。
階段のバリアフリー工事は介護リフォームが得意な業者へ
階段のバリアフリー工事を成功させるには、事前にリフォームしたい範囲や予算、目的を決めておきましょう。また介護保険や助成金制度を活用することでお得に工事ができますので、担当のケアマネジャーや介護リフォームが得意な業者へ相談することをおすすめします。