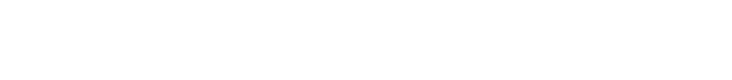日本家屋の玄関はアプローチや上がり框などの段差が多いため、車いすや高齢者にとっては家に入るのにも一苦労です。そこで玄関をバリアフリー化することで、スムーズに出入りできるようになります。今回は玄関のバリアフリー工事について詳しく解説していきます。
玄関のバリアフリー化リフォームとは?

実際に玄関をバリアフリーにしようと思ったら、どんな工事をすべきなのでしょうか?こちらではバリアフリーリフォームとは?という疑問や玄関をバリアフリーにする方法について解説していきます。
バリアフリーリフォームってどんな工事?
何気なく使っている「バリアフリー」という言葉には、バリア(障壁)となるものをフリー(取り除く)という意味があります。すなわちバリアフリーリフォームとは高齢者や障害を持つ人が生活するうえでの障壁を取り除き、快適で住みやすい住宅にする目的の工事です。具体的には下記の工事がバリアフリーリフォームとされています。
- 廊下幅の拡張
- 階段の勾配を緩くする
- 浴室やトイレの改修
- 階段や廊下へ手すりを付ける
- 部屋間の段差を解消する
- 室内扉を引き戸へ改修
- 滑りにくい床材へ変更する
自分の親や家族のために住宅をバリアフリーにしようと考えている方が多いと思いますが、ゆくゆくは自分自身のためにもなる工事だということを覚えておきましょう。バリアフリーリフォームは現在のためだけでなく、将来のためにも有効な工事なのです。
玄関周りをバリアフリーにするには
では玄関をバリアフリーにするにはどんな工事があるのでしょうか?自宅の玄関を思い浮かべると良く分かるのですが、日本の住宅の玄関は段差が多いのが特徴です。そこで足腰が弱い方や車いすの利用者が玄関から屋内に入るには、次に挙げる工事が必要となります。
玄関までのアプローチのバリアフリー化
日本の一般的な住宅の床の高さは60cmほどあります。そこで玄関ドアをくぐる前までの、アプローチ部分にスロープを付けるバリアフリー工事が有効。ただし玄関スロープの勾配は緩やかでないと危険が伴います。実際にスロープを整備する際には、勾配は1/12以下が望ましいとされます。
これは水平12に対して1上がる勾配で、角度でいうと5度となります。そしてスロープの幅は車いすでも通れるように1mは必要です。もしアプローチ部分にスペースがない場合は庭や家の周囲を回るルートを考えたり、段差解消機を設置することをおすすめします。
スロープには主に二種類のタイプがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。
| スロープの種類 | 詳細 |
| 階段付きスロープ | 既存の階段の隣にスロープを作る工事。 スペースが確保できれば容易で、介助者が補助しやすい。 |
| 手すり付きスロープ | スロープと並行して体を支えるための手すりを取り付ける。 スロープが3m以上ある時は手すりがあった方がいい。 |
スロープに使う床材も様々な種類があり、それぞれに意匠性や特徴、費用相場が異なります。特にバリアフリーを目的としたスロープでは滑りにくい素材を使い、車いすの脱輪を防止する縁石を設けると安心です。
| スロープの床材 | 特徴 | 費用相場 (㎡当たり) |
| タイル | 壊れた部分の貼り替えが容易 手入れがしやすく種類が豊富 | 12,000円~ 50,000円 |
| コンクリート | 頑丈でメンテナンスフリー 掃け引きで模様を入れると滑りにくい | 10,000円~ 16,000円 |
| 天然石 | 和風住宅の玄関口に合わせられる 見た目が良い | 16,000円~ 26,000円 |
| レンガ | 洋風の質感が出せる 強度やメンテナンス度合いはコンクリートに劣る | 10,000円~ 28,000円 |
玄関ドアや軒(庇)を変更する
玄関ドアの開閉方法を変えたり、玄関部分の軒(庇)を深くする工事も、玄関のバリアフリー化に有効です。ドアを開き戸から引き戸にし、開口部分の幅を広げることで車いすでも通りやすくなります。
さらに段差を解消するために引き戸のレール部分を取り、吊り戸にする工事もおすすめ。さらに玄関の軒を最大限まで伸ばすことで、雨の日や雪の日でも濡れることなく家に入れます。
上がり框の段差を解消して手すりなどを設置
日本の住宅に見られる上がり框(かまち)の段差を解消したり、上りやすくするのもも玄関をバリアフリーにする工事の一つ。上がり框とは靴を脱ぐ土間部分と床を隔てる横木を指します。この段差が大きいと、高齢者や車いすの方が床に上るのに大変な負担となります。
そこで上がり框の段差を低くしたり、手すりを設置する必要があります。上がり框をバリアフリーにする工事はこのような内容となっています。
| 玄関のバリアフリー方法 | 詳細 |
| スローブや手すりを設置 | 玄関の上がりかまち部分に設置すると上りやすい 降りる時や靴を履く時などもバランスを崩さない |
| 収納付き踏み台を使う | 高さのある段差でもステップ階段のように上がりやすくなる 収納部分には普段掃くサンダルや靴などを収納可能 |
| 手すり付き踏み台 | 踏み台に足を掛ける際にもバランスを崩さず安心 |
| 手すり付きベンチ | 靴を履く・脱ぐ動作も腰掛けながらできるので便利 立ち上がる際にも手すりが使える |
このように段差が高い場合は踏み台やベンチなどを使い、上りやすくする工夫がおすすめです。特に踏み台と手すりを両方設置すると、より安心して玄関を使えます。
玄関をバリアフリー化する8つの方法の費用相場を解説!

玄関をバリアフリーにする方法が分かったところで、工事にかかる費用の相場についてご紹介していきます。予算に応じて効率的な玄関バリアフリー化工事を選んでみましょう。
玄関階段をコンクリートのスロープにする
玄関前アプローチに段差があるお宅は、コンクリート製の手すり付きスロープを設置しましょう。スロープを取り付けるには、既存の土間コンクリートを打設する工事やスロープ新設工事が必要です。
ご自宅のスペースや玄関の向きなどによってどんなリフォームが可能か変わってきますので、念入りな現地調査をした後に見積もりを取りましょう。一般的な費用相場はこちらです。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 土すき取り | 2,000円~/㎡ |
| 土間コンクリート打設 | 5,000円~/㎡ |
| 残土処分 | 4,000円/㎡ |
| 諸経費 | 5,000円~10,000円 |
上の表から計算すると、工事全体で40~60万円程が相場となります。手すりを設置しない場合は、ここから10~20万円程安くなります。工事期間は最短でも2~3日程度見るようにしましょう。
玄関扉を引き戸に変更する
現状の玄関扉を引き戸にする工事は、既存のドアとドア枠を解体して新し玄関ドアを取り付ける工事になります。ドア枠ごと交換する工事をはつり工法と呼び、床面の段差を解消するにはこちらの工法がおすすめです。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 玄関ドア交換工事 | 300,000円~500,000円 |
軒や庇を深くする
玄関前の軒や庇を深くする工事は、雨風に当たらないようにするだけでなく日よけや遮熱効果も期待できます。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 軒延長工事(1400mm幅) | 500,000円~ |
| 軒延長工事(1820mm幅) | 600,000円~ |
| 後付け用庇設置工事 | 30,000円~100,000円 |
上記のような軒延長工事の他に、アルミ製の後付け可能な庇を取り付けるリフォームなどもおすすめです。後付け用の庇は支柱を立てずに外壁に取り付けられるため施工も簡単です。
上がり框の段差を撤去する
上がり框の段差を解消する工事は、玄関のバリアフリー化になくてはならない工事です。特に古い住宅に場合、30センチ以上の段差がある上がり框もあります。そこで土間をかさ上げする工事が必要となるのです。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 土間かさ上げ工事 | 200,000円~300,000円 |
踏み台やスロープを設置して上がりやすく
土間かさ上げによる段差の解消には多くの費用が掛かるため難しいという方には、踏み台やスロープを設置することをおすすめします。上がり框自体には手を入れず、覆う形でスロープの設置が可能。
踏み台はさらに費用が掛からず、数千円で購入できるものもあります。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 踏み台設置工事 | 5,000円~20,000円 |
| スロープ設置工事 | 150,000円~200,000円 |
スロープなら車いすや歩行器を使った状態でも段差を超えられ、安全に室内に入れます。
腰掛けられるイスを設置
靴を脱いだり履いたりする際に、ちょっと腰掛けられるイスがあると高齢者にも安心です。ベンチタイプや折りたたんで収納できるイスなど、種類もさまざま。手すりや収納の有無、高さ調節ができるのかによっても価格が変わります。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 介護用玄関イス | 3,000円~ |
| 壁付け折り畳みイス | 20,000円~ |
実際に使う方が腰掛けやすい高さや場所を確認してからイスを選ぶようにしましょう。
手すりを取り付ける
上がり框を超える際に、体を支えられる手すりがあると便利です。手すりにはカベに直接取り付ける壁付手すりと、壁が無くても使える床付手すりの二種類があります。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 壁付手すり設置工事 | 15,000円~20,000円 |
| 床付手すり設置工事 | 30,000円~60,000円 |
さらに既存の上がり框の段差に合わせたオーダーメイドも可能です。段差の高さや使い勝手に合わせて選んでみましょう。
足元照明を追加して明るさを確保
天井からの照明では足元が良く見えないという場合には、足元照明を追加しましょう。夜や早朝などの薄暗い中でも靴の脱ぎ着に便利。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 足元照明設置・コンセント増設 | 15,000円~20,000円 |
さらに人感センサーが搭載された照明なら、いちいちスイッチを点けたり消したりしなくても自動でオンオフしてくれます。
介護保険や自治体の補助金を利用してお得にリフォーム
上でご紹介したバリアフリー工事には、介護保険や自治体の補助金を利用できます。それぞれに条件や補助割合などが異なりますので、工事の前にしっかりと調べておきましょう。
介護保険で住宅改修費の給付を受ける場合
介護リフォームやバリアフリー工事を行う場合、介護保険の「高齢者住宅改修費用助成制度」が利用できます。こちらは費用が最大20万円までの工事に対して9割の補助金が受けられる制度です。つまり実質、自己負担は1割でバリアフリー工事ができるというもの。
ただし介護保険の助成制度の対象は、このような場合のみとなります。
- 「要介護」か「要支援」の介護認定を受けている
- 改修の対象になるのは、被保険者証の住所になっている住宅をリフォームする
また対象となる工事は、玄関リフォームに関しては次のような内容になります。自分の予定している工事が、含まれているのか確認してください。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 扉の交換
- 滑りにくい床材への取替え
そして介護保険の制度を利用する際には、下記ような流れで進んでいきます。
- 介護認定を受ける
- 担当のケアマネジャーへ相談する
- 施工業者・ケアマネジャー立ち合いの元で工事内容を打ち合わせ・契約
- 事前申請に必要な書類を提出し、審査結果を確認
- 工事着工
- 工事終了後に工事費をいったん支払う
- 領収書や工事費の内訳書、改修完了確認証を提出し介護保険へ申請
- 住宅改修費の支給を受ける
この支給方法の特徴は「償還払い」であるということです。 利用者が一度施工業者に工事費を全額支払い、そのあとで市区町村から費用の9割が後から支給されます。つまりいったんは費用を全額準備しなければならないことを忘れないように注意しましょう。
自治体の補助金には支給要件がある
介護保険の助成制度以外にも、市区町村単位で補助金を出している場合があります。こちらの制度では支給の条件や支給上限額、工事内容がお住いの自治体によって異なっています。
中には介護保険との併用が可能な制度や、介護保険を利用していないことを条件としたものまであるので、事前に確認することをおすすめします。
各種税金の減税制度を利用する
「バリアフリー特定改修工事特別控除制度」では、該当する工事を行い確定申告をする所得税が減税されます。受け取る時は還付金という名目で、おさめた所得税の一部が戻ってきます。こちらの制度が利用できるのは以下の条件に当てはまった場合となります。
- 50歳以上
- 要介護・要支援の認定を受けている
- 所得税法上、障がい者と認定されている
通常の確定申告のシーズンに、必要書類を所管の税務署に持参して申告を受けると還付金という形で所得税が一部戻ってくる制度です。
玄関のバリアフリーリフォームの業者はこう選ぶ!

バリアフリー工事は普通のリフォーム工事と違い、介護保険などに詳しい業者に施工してもらう必要があります。そこで業者の選び方をご紹介していきますので、参考にしてください。
担当のケアマネジャーに紹介してもらう
介護保険を利用している場合、担当のケアマネジャーに相談すると介護リフォームが得意な業者を紹介してもらえます。そのような業者は実績もあり、どんな点に注意して工事を進めるべきかをよく理解しています。
また煩雑な申請書類の作成や、添付する写真の準備なども任せられます。もしリフォームをお願いできそうな業者が見当たらなかったら、担当のケアマネジャーに一度相談してみましょう。
介護リフォームが得意な業者に依頼
ホームページやチラシで見つけた業者の中に、介護リフォームの実績がある業者がいたら依頼するのも良いでしょう。その際には予算に応じた提案をしてくれるか?というポイントの他にも、建築士や福祉住環境コーディネーター等の資格を持つ人間がいるかどうかも重要に。
さらに補助金や助成金について詳しく理解し、利用可能な会社かどうかも忘れずにチェックしましょう。
複数の業者から見積もりを取る
介護保険や助成金などで自己負担は少なくなるとはいえ、工事費用はなるべく安い方がいいに越したことはありません。そこで2~3社ほどの介護リフォームが得意な会社から、相見積もりを取ることをおすすめします。
相見積もりは業者同士を競わせて金額を安くできるだけでなく、工事の相場を知れたり、業者の対応を見れる点でも有効です。バリアフリー工事を成功させたいなら、まず業者選びから始めてみましょう。