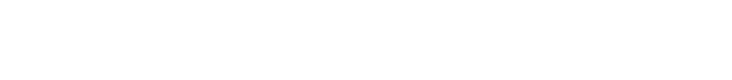古くなって歩くとギシギシ鳴る床を張り替えたいとお考えの方はいませんか?今回は床板を張り替える場合の費用を抑えるポイントや、フローリングの種類について詳しく解説していきます。
床板の張り替えの前に!フローリングについて詳しく知ろう

一般の住宅で最もよく目にする床材と言えばフローリングですが、そのフローリングには様々な種類があることをご存知ですか?使っている木の種類による違いや構造の違いにより特徴や価格、見た目などが大きく異なります。
フローリングには二種類ある
フローリングには構造の違いにより「無垢フローリング」と「複合フローリング」の二種類があります。住宅に広く普及しているのは複合フローリングの方ですが、最近では無垢フローリングも人気があります。
無垢フローリングは木の温かみが感じられる
無垢フローリングは単層フローリングとも呼ばれ、JAS規格では無垢材や集成材などの天然木のみを使ったフローリングと決められています。木の種類や木材を張り合わせた集成材の種類はとても豊富で、バリエーション豊かな中から選べるのも無垢フローリングの大きな魅力です。
【無垢フローリングのメリット】
- 天然木の手触りや香り、質感が感じられる
- 調湿効果があるため、湿気を吸ったり放出してくれる
- キズが出来ても削って補修できる
- 柔らかく足への負担が少ない
- アレルゲン物質を使っていないので、アトピーやアレルギー体質の方におすすめ
天然木ならではの風合いを感じられる一方で、このようなデメリットもあります。
【無垢フローリングのデメリット】
- 収縮や反りが発生し隙間ができやすい
- 水やキズに弱いためこまめなメンテナンスが必要
- 色のバラツキが多く統一感を出しにくい
- 複合フローリングより費用が高い
複合フローリングは強度と費用の安さが特徴
複合フローリングとはベニヤや集成材の上に、0.5~3mmほどの厚さの天然木やシート状の表面材を張り合わせたものです。昭和40年代に集合住宅が多く建てられるようになった頃から出回りはじめ、昭和60年代には畳に変わる床材の代表格となりました。
複合フローリングのメリットやデメリットはこちらです。
【複合フローリングのメリット】
- 反りや収縮がなく安定している
- 耐衝撃性や耐摩耗性が高い商品がある
- 色やデザインが豊富で様々なバリエーションから選べる
- 価格が安く施工費を抑えられる
【複合フローリングのデメリット】
- 傷が付くと修復が難しい
- 調湿効果がない
- 表面材が硬いため長時間の立ち仕事では足が痛くなりやすい
複合フローリングのメリットはそのままに、無垢フローリングのような風合いを出したい方は、表面に貼る天然木を厚めの種類にすると良いでしょう。
無垢フローリングと複合フローリングでは、それぞれに特徴がありメリットやデメリットが異なります。自分の家族構成やライフスタイルに合わせて選ぶようにしましょう。
フローリングに使用する木の種類でも色や特徴が違う
フローリングに使用している木材の種類でも色や木目の出方、硬さや耐久性が異なります。ここでは木材の種類を「針葉樹」と「広葉樹」に分けて見ていきます。
針葉樹のフローリング
針葉樹とは冬でも葉が落ちない種類の木で、スギやヒノキなど日本でも多くの種類が栽培されています。主に無垢フローリングに採用され、広葉樹に比べて含んでいる空気の量が多いため木材自体が柔らかいのが特徴。
また針葉樹は成長が早く比較的まっすぐ伸びるため木目が通っていて加工がしやすいというメリットがあります。建築用材に適しているため国内でも盛んに植林が行われてきました。
| 木の種類 | 特徴 |
| パイン | 全体的に白っぽい中に赤みがかった節が並んでいる。 カントリー風のインテリアにおすすめで、柔らかく加工しやすいのが特徴。 |
| ヒノキ | 油分を豊富に含んでいるため水をはじきやすく風呂材としても人気。 日本では最高峰とされている木材で色艶や香りは抜群。 |
| スギ | 赤っぽい中に節のある素材感が特徴。 キズは付きやすいが柔らかく温かい触り心地で人気の床材。 |
| アカマツ | 年輪がはっきりとしている独特な木目の美しさと色つやが特徴。 古くから高級木材として珍重されてきた。 |
| カラマツ | 樹脂成分が多いため耐水性や強度が高いのが特徴。 赤味の鮮やかさとハッキリとした節目が人気の床材。 |
広葉樹のフローリング
一方の広葉樹は針葉樹に比べて硬いのが特徴です。表面にキズが付きにくく収縮や膨張しにくいのも広葉樹のメリット。複合フローリングの表面材に多く使用されているだけでなく、古くから船の甲板や高級家具として加工されてきました。
| 木の種類 | 特徴 |
| ウォールナット | 重厚感のある濃いめの色と美しい木目が特徴。 床材の定番で、加工しやすく幅広い年代に支持されている。 |
| ヨーロピアンオーク | どんなインテリアにも合わせやすいオーソドックスな床材。 無垢の素材感を感じる木目を生かした部分が人気。 |
| インドネシアチーク | 高級家具や船の甲板にも使用され、耐久性や耐水性が高い。 温度変化にも強いため狂いが少なく寸法安定性に優れている。 |
| メープル | 明るい白っぽい色味が特徴で光を当てると絹のような光沢が出る。 きめ細やかな木目で、耐摩耗性が高くキズになりにくい。 |
| クリ | 古くから日本家屋の土台材として使用されてきた木材。 しっかりとした木目と黄色がかった色味はナチュラル感がある。 |
| ヤマザクラ | すべすべとした肌触りと赤みを帯びた色味が特徴。 硬すぎない足触りで、素足で歩く日本住宅に向いている。 |
フローリングの寿命は20年程度
フローリングの寿命は20年~25年程度のため、寿命が来たフローリングは張り替える必要があります。自宅のフローリングにこのような症状が床に現れた場合は、早めの貼り替えをおすすめします。
- 床鳴りがする
- 床材に汚れや黒ずみ、剥がれがある
- 床材が変色して色むらがある
- 歩くと床が沈み込む
- 大きな傷があり下地が見えている
重い家具を長期間置いている場所や、人がよく通る場所のフローリングは思った以上に劣化していると考えましょう。特に床鳴りや剥がれといった症状が現れている場合は、下地自体が傷んでいる場合があります。速やかにフローリングを剥がして下地のチェックが必要です。
床板の張り替え工事には重ね張り・張り替え工法がある
床板を一新するリフォーム工事には既存の床材の上から新しいフローリングを張る「重ね張り工法」と、古い床材を剥がして新しいものを施工する「張り替え工法」の二種類があります。それぞれのメリット・デメリットについて見ていきましょう。
重ね張り工法のメリット・デメリット
既存の床はそのままに、新しい床材を重ねて張るのが重ね張り工法です。重ね張り工法のメリット・デメリットはこちらです。
| メリット | デメリット |
| ・費用や工期が抑えられる ・ホコリや音が立ちにくい ・床が二重になり強度が増す | ・床に段差ができてしまう ・床の状態によっては工事ができない ・ドアの開閉に影響を及ぼすことも ・下地の劣化を補修できない |
既存の床を剥がす手間がかからないため、当日中に工事が終わり費用が抑えられるなどのメリットがあります。ただし床に6~15mmほどの高さが出てしまうため、高齢者のいるお宅では段差でつまづく恐れが。
さらに床の下地を露わにできないため、傷み具合を確認したり腐食を補修することが不可能です。もし床材に沈みや床鳴りなどの症状がある場合は、重ね張り工法ではなく張り替え工法をおすすめします。
張り替え工法のメリット・デメリット
既存の床材を全て撤去して新しいフローリングを張る張り替え工法では、次のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット |
| ・下地の状態を確認し、補修できる ・床材の種類を変えたお時に適している ・床鳴りや凹みが解消できる ・段差がなくきれいに仕上がる | ・既存の床材を撤去するため費用が高くなる ・工事の手間がかかるため工事日数がかかる |
張り替え工法では下地の状態を確認でき、床の高さが変わらないのが大きなメリットです。最後に張り替えてから20年以上経過している場合や、ひどい床鳴りがする時には下地をチェックして新しく張り替えるこちらの方法を選びましょう。
床板の張り替えにかかる費用の相場や日数とは?

実際に床板を張り替える場合にはどのくらいの費用や工事日数がかかるのでしょうか?二種類の工法ごとに詳しく見ていきましょう。
重ね張り工法の費用相場や工事日数
重ね張り工法の費用相場は下記の通りとなります。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 1畳当たりの単価 | 2万~5万円 |
| 4.5畳 | 5万~10万円 |
| 6畳 | 6万~14万円 |
| 8畳 | 8万~18万円 |
フローリング材の種類にもよりますが、1畳当たりの単価は2万~5万円程が相場。6畳の部屋だと6万~14万前後、8畳では8万~18万円ほどかかります。
防音性能のあるフローリング材では上記の金額にそれぞれ3万円程余分にかかることになります。工期は8畳の部屋でも半日~1日程度で済みます。
張り替え工法の費用相場や工事日数
張り替え工法では、重ね張り工法では必要なかった既存床材の撤去、処分費用がかかりますのでこのような費用相場となります。
| 工事内容 | 費用相場 |
| 1畳当たりの単価 | 3万~6万円 |
| 4.5畳 | 8万~15万円 |
| 6畳 | 10万~18万円 |
| 8畳 | 12万~20万円 |
1畳当たりの単価は3万~6万円前後、6畳では10万~18万円で8畳では12万~20万ほどが平均の価格となります。
工事日数は6畳の洋室を一人の職人が施工する場合、巾木の交換まで含めると1日~2日前後となります。ただしマンションなどでコンクリートスラブに直接フローリングを張りつけている場合、強力な接着剤を使っているため剥がす工程に時間がかかることがあります。
床板を張り替える際の注意点
床板を張り替えるリフォーム工事ではいくつかの注意点があります。お住いの住宅の種類や下地の状態によっては以下のようなことに気を付けましょう。
下地の傷み具合によっては補修工事が必要
床板の下地が傷んでいる場合には、床の張り替え工事と同時に下地ごと交換したり補修工事をすることで住宅を長持ちさせることができます。
床板や下地が劣化する主な原因は高温や多湿です。特に湿った空気が下地と床材隙間に入り込むと、下地が腐食し始め床が沈んだり歩くとフカフカする要因となります。また床の水漏れをそのまま放置しておくと、最悪の場合床が抜けるなどの被害が発生することも。
このように下地が劣化すると、構造自体に悪影響を及ぼすだけでなく大規模な工事となり費用も高額になります。定期的な床材の張り替えを行うことで下地の状態をチェックしたり、劣化が激しくないうちに補修をすることが可能となります。
マンションでは規約を確認する
マンションでは管理規約に使用できるフローリング材の遮音等級が決められている場合があります。壁や床で周囲の家に接しているマンションでは戸建て住宅とは異なり、床や壁の防音対策が求められます。
通常フローリング材の遮音等級はL値(L-Level)で表されます。これは床の衝撃音をどの位遮断できるかを数値化したもので、L値が低ければ低いほど遮音性が高いということになります。
| L値の数値 | 詳細 |
| L-50 | 走り回る足音が小さく聞こえる。 上階の生活状況が意識され、歩行音や椅子を引きずる音が分かる。 |
| L-45 | 走り回る足音は若干聞こえるが意識することはあまりない。 大きな物音や硬いものを落とすと気が付く程度。 |
| L-40 | 走り回る足音は遠くからかすかに聞こえる程度。 上階に人がいる気配はするが、物音はほとんど気にならない。 |
マンションではL-45~40の遮音等級のフローリングを採用することを求められます。まれに畳からフローリングへのリフォームを禁止しているマンションもありますので、事前にお住いのマンションの管理規約を確認しましょう。
またマンション内での工事は作業の際に出す音により、近隣住民と騒音トラブルに発展することも考えられます。管理規約には大規模なリフォーム工事の際には上下左右の部屋の住人の同意書を必要とすることを定めていることもあります。
マンションでの床板張り替えリフォームでは、管理規約にのっとった遮音性のある床材を使用して、工事中の騒音に配慮が必要となります。
DIYで床板を張り替えるのは大変
業者に床板を張り替えるリフォーム工事を依頼すると高額な費用がかかるからと、自力でDIYで作業をしようと考えている方がいるかもしれません。しかし素人がDIYで床板を張り替えるのはかなり難易度が高いということを覚えておきましょう。
床板を途中まで剥がしたはいいが思った以上に下地が劣化していて、腐った下地をどうにかしなければいけなくなることがあります。床板工事の問題点として、工事を途中で止められないという点が挙げられます。一度床板を剥がしてしまうと、張り替えが終わらない限りその部屋を使えなくなります。
既存の床板を剥がして新しい床板に張り替えるだけでも大変なのに、さらに下地の交換や補修まで必要となったら素人の手に負えなくなるはずです。途中で業者に依頼するにしても、中途半端な状態からではかえって費用が高くつくことも。
床の水平を測ったり、隙間なく断熱材を床下に敷き詰めるのもプロの技術が必要です。ここは安心をお金で買うと考えて、リフォーム会社や工務店にお任せすることをおすすめします。
賃貸住宅では敷くだけのフローリング風がおすすめ
お住いの住宅が賃貸物件なら、敷くだけでフローリング風にできるクッションフロアやウッドカーペットがおすすめ。既存の床材の上に釘や接着剤などを使わずに置くだけでフローリング風へ変えられるので、退去時の原状回復にも手間取りません。
物件の床が古いのを隠すにも有効ですし、新築物件の床を傷つける心配がありません。引っ越しの際には持ち運びができ、繰り返し使えるのでリーズナブルにフローリングにできます。
床板張り替え工事の費用を抑えるポイント

最後に床板の張り替え工事の費用を安くするポイント3つをご紹介していきます。これから床板のリフォームをしたいとお考えの方は参考にしてください。
部分張り替えや重ね張りを検討する
床板のキズや凹みなどの劣化がそれほど激しくなく、下地にも問題なさそうなら部分張りや重ね張りを取り入れてみてはいかがでしょうか。既存の床材を撤去する張り替え工法と違い、工事費用をかなり抑えることができます。
ただし重ね張りでは床材の高さが6~15mmほど上がってしまうため、隣の床との段差が生じてしまいます。また床下地の補修ができないため床鳴りや床を踏むと沈む場合は、張り替え工法を選ぶことをおすすめします。
自社施工の業者に依頼する
施工費を大きく抑えるには、自社で施工する比較的小規模の業者に依頼しましょう。というのも自社施工なら、下請けに支払う手数料やマージンが発生しないため人件費を抑えられます。
さらに比較的小規模な地元の工務店やリフォーム会社なら営業マンなどを置かず、広告や宣伝に費用を掛けない分工事費を安くすることが可能になります。床の貼り替えを得意としている業者なら、独自のルートで床材を安く仕入れたりすることもできます。
床暖房工事や断熱材工事と一緒に行う
床板を張り替えようと想ったら、一緒に床暖房工事や断熱工事をしましょう。別々に工事するよりも費用を抑えられますし、冬の足元が冷えて快適に過ごせない住宅には床暖房工事や床断熱工事が有効です。
これらの工事には床板を剥がす必要があるため、そのタイミングで床板も交換すると大幅に費用が安く済むという方法です。特に床暖房を設置する場合は、床の材質によって熱伝導率が変わるため、床が暖かくなるまでの時間が違ってきます。
また無垢フローリングは温度の変化や湿度によって膨張や収縮してしまうため、床暖房には向きません。床暖房にする時には、それに適したフローリングを選ぶことで効率的に室内を温めましょう。