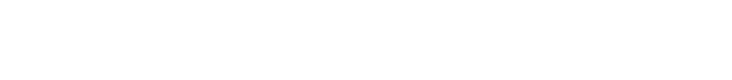良く手入れされた天然芝の庭は、見た目にも美しく優しい踏み心地と相まってとてもリラックスできる場所です。そんな芝生の張り方や選び方などを今回はご紹介。いつかは自宅の庭に芝生を張りたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
芝生を上手に張るには?芝生の張り方や選び方などの基礎知識

芝生の庭にリフォームするには、お住いの地域や日当たりに応じた芝生を選ぶ必要があります。また芝生の張り方を選び、張った後は適切に水やりや手入れをする必要も。まずは芝生の種類や芝生の張り方や手入れ方法に関する基礎知識について解説していきます。
芝生には日本芝と西洋芝の二種類ある
芝生にはその原産地に応じて日本芝と西洋芝の二種類があります。それぞれ生育に適した環境や生長時期が異なりますので、お住いの地域の気候や日当たりに適した芝生を選びましょう。
日本芝の種類と特徴
日本芝とはその名前が表わす通り、日本の高温多湿の気候で生長する芝生のこと。日本芝は暖冬型でもあるため11月~3月の冬期間は枯れて茶色になりますが、春になると再び芽吹き、青々と茂ります。
日本芝の適温は25~35度前後ということで高温や乾燥にも強く、病害虫が付きにくいため一般家庭でも比較的管理しやすい芝生です。日本芝は主に4種類。それぞれの特徴はこちらになります。
| 芝生の種類 | 特徴 |
| 野芝(ノシバ) | 北海道より南の日本全土で生えている野草の一種。 公園などでよく見られ、葉の幅が広く丈夫な性質。 観賞用の庭にはあまり向いていない。 |
| 高麗芝(コウライシバ) | 東北以南で生育可能なポピュラーな園芸種。 乾燥や肥料不足でも生育し、冬は枯れるが4月ごろから再び緑色になる。 葉の幅は野芝よりも細く刈り込みによってきれいな仕上がりになる。 |
| 姫高麗芝(ヒメコウライシバ) | 高麗芝よりもさらに葉の密度が濃い柔らかい見た目の芝生。 生育が早いためこまめな手入れが必要になる。 |
西洋芝の種類と特徴
一方の西洋芝は北海道などの冷涼な気候で良く育ちます。西洋芝には暖地型と寒地型の二種類がありますが、メジャーな寒地型の適温は15~20度前後。そのため夏場に30度を超える日が何日も続くような地域では、芝生が弱って枯れてしまいます。
とはいえ冬に枯れない西洋芝は一年中青々とした色を楽しめます。多くのゴルフ場のグリーンで使われているのも西洋芝です。
お手入れは日本の代表的な高麗芝と比べて、刈り込みなどのこまめな管理が必要となります。芝生の管理に自信がある方は西洋芝を選んでみては?
| 芝生の種類 | 特徴 |
| バミューダグラス(暖地型) | 日本芝よりも早く成長し、ゴルフ場だけでなく一般家庭でも採用されつつある。 日陰の生育が難しく、生長スピードが早いためこまめな芝刈りが必要。 |
| ベントグラス(寒地型) | 耐暑性、耐寒性に優れているが病害虫に弱いため管理に手間がかかる。 かなり短い刈込にも耐えるためゴルフ場のパッティンググリーンに使用されている。 |
| ブルーグラス(寒地型) | 世界で最も栽培されている芝生の種類。 踏み圧に強く、寒冷地や半日陰でも育つ。 さび病が発生しやすい、発芽や生育が遅いのがデメリット。 |
芝生を張る前に庭の土質や生育環境をチェック!
芝生には生育に適した土質や環境というものがあります。芝生を張る前にキチンと土壌を整えてあげないと、芝生が枯れてしまったり思うように育たないことも。芝生には下の3点が重要となります。
- 水はけがよい土壌
- 日当たりのいい環境
- 風通しが良い場所
日当たりや風通しは庭のある方角や建物の立地によって変えられませんが、一日で5時間以上日が当たる場所であれば問題ありません。また1番目の土壌は改良することで、芝生を張るのに適した水はけにできます。
こちらは庭の土壌の改良方法を示した一覧です。
| 土質・環境 | 特徴 |
| 粘土質 | 土の酸度が高く空気や水を通さないため、芝生の生育に向かない。 広範囲に土を掘りだして川砂や元肥、有機石灰を混ぜ合わせると改善する。 |
| 砂土 | 日本芝の生育に適しているが西洋芝には乾燥しすぎる環境のため向かない。 西洋芝を植える場合はピートモスや畑土などを加えて改良する。 |
| 水はけが悪い | 芝生を張ると根が腐りやすく、コケなどが生えるため向かない。 地面に勾配を付けたり地中に溝を掘って透水管を埋める作業が必要。 |
| 大きな石がある/ 凹凸がある | 地面に凹凸があると水たまりになりやすく、石がある場所では生育しにくい。 古いなどで大きな石を撤去して、凹凸はレーキなどで平らにならす。 |
芝生張りに必要な道具や材料
芝生を自分で張ろうと思っている方に、必要な材料をご紹介していきます。お近くのホームセンターなどで必要なものを揃えられますので、芝生張りに自信のある方はチャレンジしてみてください。
| 材料の名称 | 詳細 |
| 切り芝(ソッド) | 20×30㎝のマット状の芝生で、1×2mの面積では3束必要になる。 |
| 川砂 | 水はけの悪い土には川砂を混ぜて土壌を作る。 粘土質の土壌で多く使用する。 |
| 培養土 | 元肥として土に混ぜる場合に使用。 |
| 目土(めつち) | 芝生の凹凸をなくし、生長を促進させる役割を持つ土。 目土専用の土を使用し、レーキなどで広げてそのあと水やりをする。 |
次に芝生張りに必要な道具をご紹介していきます。
| 道具の名称 | 詳細 |
| スコップ | 土壌づくりでは7㎝ほど地面を掘り起こすのに使用。 |
| レーキ | 土の凹凸を均すのに必要で、広範囲の芝張りには便利。 |
| 古い | 目土をふるうのに使う。 |
| 散水ホース | 切り芝を並べる前の地面や並べた後の水やりに使う。 |
上で紹介した材料や道具は、芝生張りに最低限必要なものです。芝生を張る前の土壌をより均一にならしたり、芝生を均等に並べるには専門の道具が必要となります。
また芝生を張った後の芝刈り機やエアレーションの道具も自分で管理するには、持っていた方が良いでしょう。
芝生の張り方には4種類ある
自分で芝生を張るにしろ、業者にお任せするにしろ芝生の張り方を選ばなければなりません。基本的に芝生を張る際は、マット状になっている「切り芝(ソッド)」というものを一列ずつ並べていきます。
張り方は一列目を張ったら、次の列は芝生の切れ目が揃わないようにわざとずらして張っていきます。これは切れ目を揃えて張ってしまうと芝生が安定せず、隙間が広がってしまうため。芝生の張り方には主に4種類があります。
| 芝生の張り方 | 特徴 |
| ベタ張り | 隙間なく切り芝を並べていく張り方。 隙間がないため雑草が生えにくいが、使う芝の量が多く費用が高くなる。 |
| 目地張り | 切り芝の間にそれぞれ3~5㎝ほどの隙間を開ける張り方。 ベタ張りの80%ほどで張れ費用は抑えられるが、芝が成長するまではこまめな雑草取りが必要。 |
| 市松張り | ベタ張りの半分ほどの芝で済み、市松模様のように一つ飛ばしで張る。 隙間が大きく開くため、全面を芝にするにはかなりの時間がかかる。 |
| 筋張り ・一条張り | 一列をベタ張りで張ったら、二列目は飛ばして三列目を張っていく。 芝張りにかかる時間や費用を短縮できるが、全面芝にするには時間がかかる。 見た目も良くないため、一般家庭ではあまりおすすめできない。 |
芝生の張り方の手順を解説
次に芝生の張り方の手順を簡単にご紹介していきます。
- スコップで7㎝ほど掘り起こし、雑草や石ころを取り除き土が柔らかくなるまで耕す。
- 芝生を張る部分に水はけのよい川砂などを混ぜて土を作る。
- 地面に凹凸が出来ないように整地。全体的に少し傾斜を付けると水たまりができにくくなる。
- 足を使って踏み固め、芝を並べる前に水を撒いておく。
- 均した地面に切り芝をずらしながら並べる。
- 芝生の上に板を敷き、圧力をかけて地面と根を密着させる。
- 芝生の上からふるいにかけた目土を敷き、細かい凹凸や芝生の隙間を埋める。このとき土で葉が隠れないようにする。
- レーキなどで目土を芝にすりこむ。
- 直後にたっぷりと水をやる。根付くまでは乾燥しやすいためこまめに散水をする。
芝生を張ったら二週間は、水やり以外では芝生に入らないようにしましょう。
張った後の水やりや管理の方法
芝生を張った後は水やりの頻度が重要となります。高麗芝は週に一度ほどたっぷりと水やりしてください。冬場は休眠期となるため基本的に水やりは必要ありません。
西洋芝は緑が最盛期になる初夏から秋にかけて頻繁に水やりします。夏場は基本的に毎日水やりが必要で、秋は状態を確認しながら2~3日に一度程度の水やりをします。
水やりをする時は芝生の底の土まで水が染み込むくらいにしっかりとあげてください。こちらは水やり以外の芝生の管理方法です。
| 芝生の管理方法 | 詳細 |
| 芝刈り | 【日本芝】5月~6月・10月は月一度程度。7月8月は月に2~3度2㎝の高さに刈る。 【西洋芝】3月~6月・9月~10月は月3~5回、7月8月は月1~3回程度 |
| エアレーション | 踏み固められた芝生に穴を開けて通気性を良くする作業。 専用の器具を使い一年に一度、夏ごろ行うと良い。 |
| 目土入れ | 芝生を踏むとぶかぶかしている場所に目土を入れ込む。 芝生の凹凸をなくすための作業で、除草した後に春から初夏にかけて行う。 |
| 施肥 | 芝の種類に応じた肥料を与える。 高麗芝では春に色づいたら1度、後は二か月に一度程度。 西洋芝は3~4月に1度、5月6月に各一回づつ、後は二か月に一度程度。 |
| 除草 | 芝生の間に生えた雑草や枯葉はこまめに手で取る。 子供やペットが遊ぶ庭では除草剤の使用は控える。 |
芝生を張るには適した季節がある
芝生を張るには適した季節というものがあります。日本では3月中旬~6月が適しています。雪の多い北日本では4月以降が良いでしょう。
芝生が根付きやすく徐々に温度が上がるにつれ生長しやすくなります。梅雨時期には多少の雨でも根がズレることがありません。どうしても春に植えられない場合は9月~10月に植え付けると良いでしょう。
芝生張りはDIYでもできる?
芝張りの手順を見ると、意外に簡単そうで自分でもできるかも?と考える方もいるかもしれません。ただし芝生は植物ですので植物に関する知識や土壌改良の方法を熟知していないと芝生が枯れてしまうことも。
また作業道具や手入れ道具を全て揃えるとなるとかなりの費用が掛かってしまいます。そのため業者に依頼した方が、結果的に手間や時間を節約できることにつながります。
芝生の価格と業者に依頼する際の費用相場を解説

ここでは芝生張りやメンテナンスを業者に依頼した際の費用相場を解説していきます。
芝生張り工事・メンテナンスの費用相場
芝生のみの価格は㎡当たり3,500円~6,000前後が相場となります。
| 工事内容 | 費用相場(㎡当たりの単価) |
| 芝張り | 5,000円~10,000円 |
| 芝刈り | 1,000円~2,000円 |
| エアレーション | 2,000円~3,000円 |
芝張りの相場は材工共で5,000円~10,000円前後です。芝刈りは㎡当たり1,000円~2,000円。エアレーションは2,000円~3,000円となります。
ただし古い芝を撤去する場合は、その処分費用も追加でかかることがあります。
業者に依頼する芝生張り費用を抑えるコツとは?

業者に芝生張りを依頼する場合、なるべく費用を抑えるにはいくつかのポイントがあります。
古い芝生は自分で剥がして処分
古い芝生を自分で剥がして処分すると、その処分料を節約できます。先ほど少し触れましたが既存の芝生を剥がして処分する費用は別料金になる場合がほとんど。業者に依頼するとゴミ袋1つで1,000円前後の料金がかかります。
そこで自分で芝生を剥がして、自治体のごみ処分センターなどに持ち込めば費用がかからず処分できます。可能であれば剥がした後に砂利を取り除いたり、整地しておけばさらに費用を抑えられます。
相見積もりを取って価格をチェック
芝生張りのみならずリフォーム工事を業者に依頼する場合は、必ず2~3社から見積もりを取って相場価格をチェックしましょう。同時に工事内容の説明が分かりやすいか?見積書の数量は明快か?なども確認して、相性の良い業者を探してください。
芝生張りは植栽が得意な業者にお願いしよう
芝生は一度張ってしまうと土の入れ替えをするのは困難になります。つまり張る前の土壌づくりが大きなポイントに。できれば芝生張りや適した土壌づくりに慣れた業者に依頼して、芝生が伸び伸びと育つ環境にしてあげましょう。